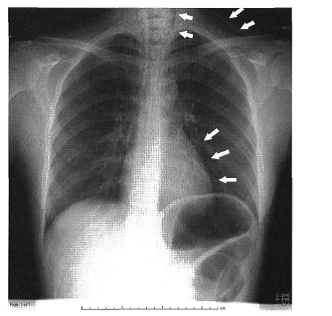要介護高齢者に対する機能的口腔ケアと血漿中活性型グレリン値の関連性
九州歯科学会雑誌に「 要介護高齢者に対する機能的 口腔ケア と血漿中活性型グレリン値の関連性 」 (木村貴之, 遠藤眞美, 永富絵美, 久保哲郎, 林田裕, 柿木保明 66(2): 29-38, 2012. )が掲載されている。 要旨は「わが国では要介護高齢者が増加しており, 非経口摂取者も増加していると考えられる. 近年, 要介護高齢者に対して日常生活の維持・向上にもつながる機能的口腔ケアを行うことが重要とされ, 歯科医療従事者が非経口摂取者を含む要介護高齢者に関わる機会が増加してきた. グレリン は, 主に胃から産生されるペプチドホルモンで, 成長ホルモン分泌促進や摂食亢進を担うとされており, 老年医学やリハビリテーションの分野において, これらの生理作用が期待され, 近年注目されてきた. 咀嚼時の口腔刺激は消化管運動を誘発 するとされることから, 口腔ケアによる口腔感覚や唾液分泌がグレリン分泌改善 につながると考えられた. そこで, 非経口摂取の入院中要介護高齢者に対して機能的口腔ケアを実施し, 血漿中活性型グレリン動態との関連性について検討した. 実施前は変化が少ない平坦な血漿中活性型グレリン濃度変化曲線であったが, 実施1ヵ月後では食前の濃度上昇, 食後の濃度降下が認められるようになり, より生理的な濃度変化に改善した. 血漿中活性型グレリン濃度変化が, 非経口摂取の要介護高齢者に対する機能的口腔ケアにより改善する可能性が示唆された. さらに, 口腔ケアアセスメントとの相関が認められたことから, 血漿中活性型グレリン濃度は要介護高齢者における機能的口腔ケアの評価方法の1つとなる 可能性も考えられた. 」と述べている n数が6のため、これから多くの人数による検証が必要と考えられるが、グレリン濃度向上のため機能的口腔ケアを行うことは、摂食意欲の増進のため重要であると思われた。なお、今回使用されている口腔アセスメントシートは SAKODA式アセスメントシートを改良したもの述べている。迫田式アセスメントシートは聞いてはいたが、実際に評価に