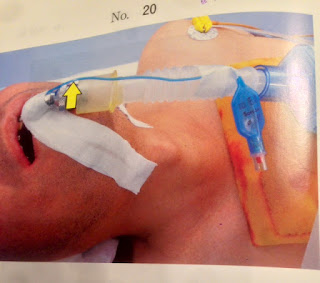Rehabilitation of swallowing and cough functions following stroke: an expiratory muscle strength training trial
Archives of Physical Medicine and Rehabilitationに「 Rehabilitation of swallowing and cough functions following stroke: an expiratory muscle strength training trial 」 (Karen Wheeler Hegland, Paul W. Davenport, Alexandra E. Brandimore, Floris F. Singletary, Michelle S. Troche)が掲載されている。 Abstract Objective To determine the effect of expiratory muscle strength training on both cough and swallow function in stroke patients. Design Prospective pre-post intervention trial with one participant group. Setting Two outpatient rehabilitation clinics Participants Fourteen adults with a history of ischemic stroke in the preceding 3 – 24 months participated in this study. Intervention Expiratory muscle strength training (EMST) . The training program was completed at home and consisted of 25 repetitions per day, 5 days per week, for 5 weeks. Main outcome measures Baseline and post-training measures were: maximum expiratory pressure, voluntary cough airflows, reflex cough challenge to...